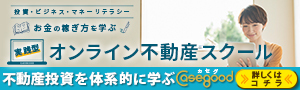不動産投資をはじめたいと思ったところで、まずいくらぐらいの価格の収益物件から購入したらいいのかわからない?
収益物件も色々ありすぎてどうしていいかわからない。
あと購入したあとにどんな費用がかかるかわからないから不安になる。
できるだけわからない部分を無くしましょう。
この記事では、いくらぐらいの価格からはじめれば危険でないのかを説明します。
不動産の価格ってどうやって決まっているの?
 まずは不動産の価格がどうやってきまっているのか紹介していきたいと思います。
まずは不動産の価格がどうやってきまっているのか紹介していきたいと思います。
評価額の種類
不動産にはさまざま評価で価格が決められています。
その評価額をもとに実際に取引する価格を決めたりします。
公示地価
国土交通省が毎年1回、土地を調査して価格を決めます。
毎年3月に価格が発表されます。
公示価格の1.2倍ぐらいが実勢価格になると言われています。
下記のサイトで見ることができます。
標準地・基準地検索システム~国土交通省地価公示・都道府県地価調査
路線価
毎年7月1日に国税庁が路線価を公表します。
路線価は道路に面する土地1㎡の価格を言います。
だいたい地価公示価格70%~80%ぐらいになることが多いです。
路線価は相続税、贈与税などの算出に使われ3年に1回評価替えが行われます。
下記のサイトから見ることができます。
固定資産税評価額
固定資産税の基準となる価格です。
路線価と再調達価格などをもとに市町村が設定します。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に固定資産税の納税通知書が送られます。
納税通知書に固定資産税評価額が記載されています。
市区町村がまたがっている場合には、2つの納税通知書で確認しましょう。
増築未登記場合などでは登記簿面積と固定資産税の納税通知書に書かれている面積と違うこともあります。
基準地価
公示地価を補完する価格で各都道府県が毎年9月に発表します。
北海道、愛知県、東京都など各地域で価格を決めています。
基準地価も公示地価のサイトから見ることができます。
鑑定の種類
実際にどれくらいの価値があるのかを鑑定します。
鑑定にはいくつかの方法がありますので紹介します。
金融機関は独自の鑑定評価をもとに融資可能額を決定しています。
原価法
原価法は再調達原価をもとに不動産鑑定を行う方法です。
再調達原価は、中古物件であれば同じものを建てた場合にはどれくらいの価格になるのかを計算して鑑定します。
建物については、経年劣化での価値が下がっている分を差し引いて価格を計算します。
構造上によっての単価を活用します。
取引事例比較法
取引事例比較法は、過去の似たような物件での取引事例をあげながら比較し評価する方法です。
宅地であれば宅地、店舗であれば店舗の複数の成約事例を使います。
最近の市場や周辺の動向や相場を相考慮して評価します。
不動産会社の中古住宅の査定などは取引事例から比較して計算することが多いです。
収益還元法
収益性のある不動産に対して使う評価方法です。
将来この不動産がいったいどれくらいの収益を生むのかをもとに計算されます。
利回りが高い物件であれば収益還元法での評価は高くなります。
不動産業者が中古の収益物件の査定などでは収益還元法での評価をもとに売買金額を決めることが多いです。
不動産価格の推移
 不動産の価格は昔と比べてなんとなく高くなってることはわかるかと思います。
不動産の価格は昔と比べてなんとなく高くなってることはわかるかと思います。
では実際に不動産の価格はどうように推移してるかを見ましょう。
全国の推移
引用:国土交通省
データを見ればわかるように区分マンションは値上がりしていてそれ以外の物件は少しずつ上昇していています。
価格指数は収益物件を購入するときのひとつの指標になります。
不動産は大きな値動きはありませんが、バブル崩壊の時みたいに急激な値下がりもしにくいのです。
区分マンションの値上がりはタワーマンションなどの高級なマンションが価格指数をあげている可能性でもあるでしょう。
全体的なイメージでは緩やかに上がっているような感じになります。
タワーマンションは加熱気味に価値があがっている傾向なので注意する必要があるでしょう。
2025年大阪万博
2020年の東京オリンピックはコロナの影響もあり不動産価値がそこまで上昇しませんでした。
2021年もコロナの存在があり不動産価値はあまり上昇しませんでした。
2025年には大阪万博の開催が予定されています。
ころからは、大阪の物件価格は少しずつは上昇することが予測されます。
周辺環境が変化する時期にはもう少しあがってくるでしょう。
ただ2025年から世帯数も減少していくことが予測されていますので地方の物件は価値が下落する可能性があります。
地方では駅から徒歩圏内での物件にするほうがいいでしょう。
今までは人口は減少していましたが世帯数は増えていたので賃貸需要は増えていました。
今後はエリアによっては不動産投資も厳しいエリアがでてくることでしょう。
コロナの影響
コロナの影響で住宅系の収益物件は値段があがっています。
考えられる理由としては、コロナの影響が少ない業者が他に投資することがなく収益物件を購入しはじめていることがあるかと思います。
新規事業をするより安定性のある不動産投資に資金が流れてきているのでしょう。
コロナの影響で事業者は運転資金の融資がうけやすかった点もあるでしょう。
金利の影響
収益物件の場合には、変動金利があがれば不動産価格は下がると言われています。
あとで紹介する返済比率に影響してくるからです。
金利が上昇することで収益性が悪くなってしまい利益が減ってしまうのです。
不動産投資するには今は低金利な状況で始めやすいのですが、ローンの期間がどうしても長くなってくるので長期的な視点も必要になります。
低金利な状況のときにいかにローンの元金を減らしておくかが大事になってくるでしょう。
物件購入はいくらぐらいの価格からはじめたらいいの?
 収益不動産の購入には、物件価格とは別に諸経費(購入金額の約7%~8%程度)がかかります。
収益不動産の購入には、物件価格とは別に諸経費(購入金額の約7%~8%程度)がかかります。
諸経費まで融資してくれる金融機関は少ないです。
なのである程度の自己資金の準備は必要になります。
まずは自分がいったいどれくらい借入できるかを把握しましょう。
不動産購入に必要な諸経費
不動産購入には物件価格以外にさまざまな費用がいります。
どういった費用が必要になるかを紹介していきます。
仲介手数料
不動産業者に支払う報酬です。
物件購入時に不動産業者に仲介してもらうのであれば必要になります。
物件価格の3%+6万円(別途消費税)が必要になります。
登記費用
不動産を購入すると、法務局に登記する必要があります。
司法書士などに報酬が必要になります。
また登記にかかる登録免許税もかかってきます。
取得税
不動産を購入してあとに取得税が必要になります。
購入時には必要ではないのですが、購入してから3ヶ月後ぐらいに納付書がきますので最初から資金を準備しておかなければいけません。
その他
火災保険料や金融機関の融資手数料、担保調査費用、鑑定費用などさまざまな費用がかかることがあります。
どのくらい融資が可能?
 出典:株式会社MFS
出典:株式会社MFS
実際に自分がいくらぐらい借りれるかわからない場合には、ヤフーグループ、マネックスグループが出資する会社にバウチャーサービスというのがある。
投資用の物件を購入する前に借入可能な金額と金利がわかる『バウチャー(借入可能額証明書)をもらえるサービスです。
せっかく買いたい物件が見つかっても金融機関から融資を承認してもらえなければ諦めるしかありません。
事前に借入額を把握しておくことによって購入する物件の価格帯を先に把握しておくことができます。
借入額がわかったとしても物件によっては希望金額まで融資承認されないこともあります。
あくまで自分が借りれる水準を知っておく目的で利用しましょう。
簡単な入力で登録無料なので事前に借入金額な金額を把握しておきましょう。
自己資金はいくら必要
金融機関では、物件価格に対して自己資金を1割~2割程度必要なケースが多いです。
自己資金が300万円であれば、1,500万円~3,000万円程度の物件が投資する物件価格の目安になります。
投資できる物件価格の金額がわかれば、次に大事なのは返済比率になります。
返済比率とは
家賃収入に対しての借入返済額です。
はじめての不動産投資では返済比率は50%がベストです。
返済比率が50%の物件がなかなか見つからなければ、返済比率を60%までに変更して探しましょう。
それ以上の返済比率になると、かなりリスクはありますのでやめておきましょう。
なぜならば不動産投資には管理コストも必要になってくるからです。
管理コストの概算内訳ですが、コストが家賃に対して40%ぐらい必要です。
管理会社に支払う費用…5%
建物管理費用…5%
固定資産税…10%
修繕費用…10%
空室損失…10%
修繕費用と空室損失の割合が多くなっています。
いかに入居者に長く住んでもらい空室損失を減らして満室経営するかが不動産投資の成功と失敗の分かれ道になります。
はじめて不動産投資する場合の基準値
はじめて不動産投資するのであれば4つの基準値をしっかり守ってさえいれば大きな失敗はしないです。
返済比率50%以内
・家賃収入が20万なら返済が10万以内
年収の8倍以内
・年収350万なら2800万以内
表面利回り
・10%以上
家賃設定
・家賃が10万以下の設定の物件
物件購入の価格は借り入れ可能額もあります。
金融機関で年収の8倍以上は貸してくれるところもなかなかないかと思います。
他に担保提供が可能であったりすれば年収の8倍以上貸してくれることもあります。
家賃設定が10万円以下に設定している意味は、もし空室期間が長くなったとしても仕事などの他の収入でなんとか金融機関に返済していくことが可能な範囲だからです。
ローンの返済は給料などから補ってでも返済して不動産を5年以上保有して売却すれば売却益で相殺できる可能性もあります。
逆に購入してから5年以内で借入が返済できなくなってしまい物件を売却すると損する可能性が非常に高くなります。

購入物件の計算例
購入物件の例を紹介していきます。
年収が350万の人が金融機関から2,000万円融資できた場合
1棟中古アパート
物件価格2,200万円
2DK 4部屋 木造築10年
1部屋あたりの家賃5万5千円
返済金額 約10万円
※借入金額 2,000万円 金利1.8%
返済期間20年
この場合、年収350万円だとしたら年収の8倍以内の2,200万円
家賃が5万5千円×4部屋=家賃収入22万円
返済は約10万円(毎月の返済金額)÷22万円(毎月の収入)=返済比率は約45%
22万(家賃収入)×12ヶ月(1年間)÷物件購入価格2,200万円=0.12 利回り約12%
すべての条件をクリアしています。
このような物件を購入できたら失敗する可能性は低いでしょう。
この場合の5年後のローンの残債は1,565万円になっています。
購入時と売却時の諸経費が10%の200万円かかったとしても、5年後に物件を2,000万円で売却できれば235万円は利益がでます。
毎月もいくらか収入があって5年後にもある程度利益があるのは不動産投資の魅力的な部分でもあります。
そんな儲かる物件なら売却しないのでは?
疑問に思うかも知れませんが、不動産投資家は売却してさらに大きな物件を購入する方が多いのです。
はじめて不動産投資する場合のおすすめ

借入が可能な順番に紹介していきたいと思います。
借入可能額によってどんな物件を購入するべきか変わってきます。
融資が5,000万円ぐらい借入可能な場合
もしある程度借入が可能であれば、中古の一棟アパートで8部屋以上の物件がいいです。
私自身も最初は築10年8部屋の木造アパートからはじめました。
いくらかは儲かって売却はしました。
8部屋あればもしどこかの部屋が空室になったとしてもローンの返済はできるので補填することなく保有するできます。
補填せずに保有できるので高値で売り出して、売れなくても毎月の家賃から返済できるので焦らずに高値で売却することができます。
なぜ8部屋かというと空室率は一般的には10%は見ておきましょうというのがあります。
8部屋×12ヶ月=96ヶ月分が年間の家賃収入です。
空室率で計算すると9.6ヶ月分はないものとして投資する前から計算してあったので1部屋の空室期間が9ヵ月でても返済に困ることはありませんでした。
空室率はあくまで平均的な数値です。
ただ区分マンションなどで1部屋だと実際に空室になれば補填しないといけない可能性が高いのです。
融資が3,000万円未満の場合
中古の分譲マンションを探しましょう。
とくに学区の良い中古の分譲マンションを探しましょう。
分譲賃貸は設備のグレードが違うので人気です。
あと学区が良ければやはり人気が高いです。
分譲マンションであれば、出口は不動産投資家だけでなく一般の住居としての購入者も対象になるので大きな失敗はしにくいでしょう。
融資が1,000万円未満の場合
DIYできるのであれば築古戸建を買いましょう。
築古戸建は利回りが高いのでキャッシュがたまりやすいです。
ただ改装費がいくらかかるのかをしっかり計算した上で購入しましょう。
DIYする時間もない場合には、中古の区分しかないのですが駅近の物件でかつ500万以内のワンルームがいいです。
1戸だと危険なのでできるだけ早くに次の物件を購入してリスクを分散しながら不動産投資を進めていきましょう。
事務所利用もしくはセカンドハウスにもできるような駅近物件がいいです。
そのような物件であれば空室になる可能性も減らせてます。
事務利用などであれば、家賃を少しぐらいならあげることが可能です。
500万円以下の金額だと物件はどうしても古くなるので管理費と修繕積立金は購入する前にしっかりと確認しておきましょう。
最後に
 まずは自分の融資してもらえる金額を把握して、その中で物件を探しましょう。
まずは自分の融資してもらえる金額を把握して、その中で物件を探しましょう。
不動産業者もどれくらいの金額でどのような利回りでと指定してくれると物件を探しやすくなります。
あとは返済比率に問題がなければ、リスクはだいぶ減るでしょう。
物件を探して買いたいと思える物件が見つかったら次に賃貸をメインでやっている不動産屋に相談しましょう。
買おうと考えてるけれど、いくらぐらいなら貸せるかを聞いておきましょう。
親切に教えてくれる業者であれば将来的に入居者募集も依頼できますのでインターネットの情報だけでなく不動産屋の声を直接聞いておくのも大事です。